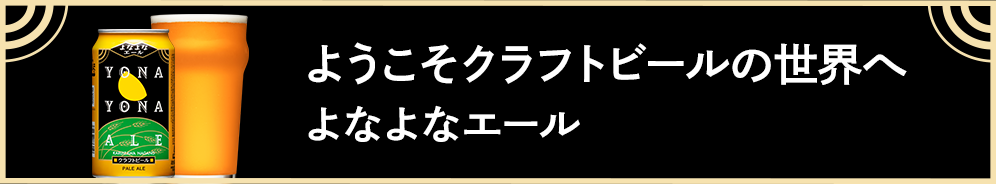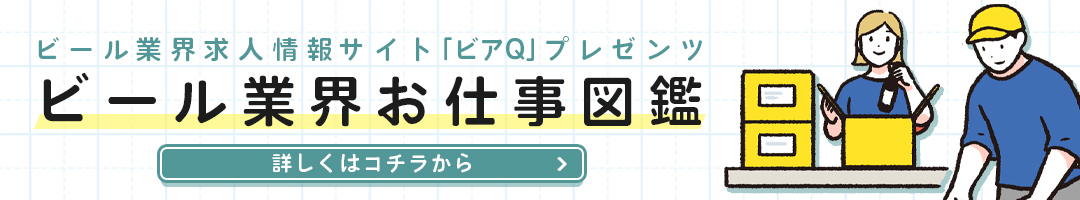【ビールエッセイ】嗚呼、愛しのクラフトビール! ~六島浜醸造所「ドラム缶会議」で沼にハマったはなし~
お酒が飲める年齢になってから、わたしの人生は常にお酒と共にあった。
大学のサークルでは誰にも求められていないのにカシスオレンジをピッチャーで一気飲みし、居酒屋のバイトの後には朝まで飲み歩いた。当時のわたしのモットーは「べろんべろんになるまで飲むのがお酒に対する礼儀」。今思えばまったくをもって意味がわからない。
大学卒業後は飲食店の店長になった。お店は蒲田にある九州料理の屋台居酒屋。そこではお客さんに奢ってもらったジョッキ片手に仕事をし、営業終了後には毎晩のように深夜営業の居酒屋に流れた。乾杯時のジョッキはほぼ一口。そしてすぐにおかわりを頼む。そりゃあもうガバガバと浴びるようにビールを飲んでいた。この当時のわたしのモットーは「杯を乾かすと書いて乾杯」。その通りだが、それをモットーにしていたからか、全くもってモテなかった。
しばらくしてわたしはワインにハマった。ワインはボトルによっていろんな表情を見せてくれるから楽しい。フランスにイタリア、スペイン、オーストラリアにチリ……ぶどうや国で味わいを想像し、実際に飲んで答え合わせをする瞬間がおもしろかった。
でもワインも同じようにがぶがぶと飲んでしまう。ワインはわたしにとって記憶が飛びやすいお酒らしく、どっぷりと飲んだ日にはよくゴミ捨て場で眠って朝を迎えたりした。当然前日に飲んだワインの銘柄や味わいなんかもすっぽりと忘れてしまう。
長いことわたしにとってはお酒は喉と心の渇きを癒し、酔うためのものだった。嫌なことを忘れ、陽気になって人の距離を縮める。そんな魔法のツールだった。
そんなお酒に関する概念がひっくり返った日のことを今でも覚えている。
クラフトビールに関する仕事をするようになり、わたし晩酌はクラフトビール一色になった。クラフトビールは美味しい。フルーツビールは本物の果実を齧ったような味わいだし、ホップがたっぷりと効いたビールは、ジューシーさがありつつもずっしりとした苦みが追いかけてくる。その表情の豊かさにわたしはあっという間に魅了された。
でもその一本に出会うまで、クラフトビールはわたしにとって「ただの美味しいお酒」だった。
ある日の夜、わたしはクラフトビールのサブスクで配送された一本のビールを開けた。

写真提供:六島浜醸造所
六島浜醸造所 ドラム缶会議
深い茶色に、炎のようなイラストのラベル。グラスに注ぐとそれはどっしりとした漆黒だった。黒ビールは好きだ。わくわくしながら匂いを嗅ぐ。するとそれは驚くことに燻製の香りだった。ふとディズニーシーのスモークターキーを思い出し、口の中がよだれでいっぱいになる。
一体どんな味わいが想像もできないまま口に含むと、それは高級な焙煎珈琲のような味わいだった。濃厚でコクがあって。それでいて呼吸をするたびに燻製の香りが広がる。もともと燻製好きのわたしはその感覚にドはまりしてしまい、なめるように味わった。ふんふんと息をしながら余韻を楽しむと、酸味と共にフルーティな甘みをも感じる。
「うっま……!!!」
美味しさのあまり、誰もいない空間に向かって声をあげ、そしてこのビールについて検索した。
六島浜醸造所は六島という岡山県最南端の離島にあり、その島は人口60人しかいないこと。ドラム缶会議とは居酒屋のない六島において、夕方島の人々が波止場に集まりドラム缶を囲んで飲む文化であるということ。そこに参加すると燻されて身体中が燻製香になり、それを表現したのがこの「六島浜醸造所 ドラム缶会議」であること。
そしてHPにはこのビールを醸造している一人の男性の姿があった。

写真提供:六島浜醸造所
ハッとした。
いままでビールを誰かが造っているなんて想像もしたことがなかったからだ。
でも写真の男性はものすごい真剣なまなざしで、大きな鍋を棒のようなもので混ぜていた。鍋と男性の熱が伝わってくるような一枚をみて、あぁこれは大事に造られたビールなのだな、そう気づいた。その瞬間手の中のボトルがずっしりと重みを増したのを覚えている。
一呼吸して次の一口を飲むと、目の前に六島の風景が広がった。それはびっくりするほどにリアルで鮮やかに。もくもくと火が立ったドラム缶を囲み、島の人々が笑っていた。

写真提供:六島浜醸造所
ビールに土地と文化までも溶かし込めるのか
衝撃だった。これは職人が造ったものなのだ。ビールのラベルを見ながらしみじみとそう思った。いままで職人は刃物を作ったり、器を作ったりする人たちだと思っていた。興味はなくはないけれど、自分の人生とは少し離れた場所にいる人たちだった。
でもこんなにも身近に職人がいたのだ。
一本のクラフトビールには溢れ出さんばかりの職人の想いと、その土地への愛情が詰まっている。そしてその一本を舌で味わうことにより、どの土地へも想いを馳せることができるのだ。
そう気づいてからお酒は「たくさん飲んで酔うもの」から、「まだ見ぬ土地へといざなってくれるガイド」へと変わった。
わたしは今日も今日とてクラフトビールを飲む。
1日1本。初夏の風を感じながら、とっぷりとした夕暮れを見ながら、深夜のシンとした無音を聞きながら。そしてクラフトビールで様々な場所に旅をする。

写真提供:六島浜醸造所
クラフトビールを飲むようになってから、1人飲みが全く怖くなくなった。それはきっと、そこにハッキリとした「造り手」の姿を感じるからだと思う。誰かの熱を感じて飲むお酒は、身体に入ったあともくっきりとその存在感を示してくれるものだ。クラフトビールはお酒というより、いまやすっかりわたしの相棒になっている。
そんなわたしの今のモットーは「クラフトビールを骨の髄まで味わい尽くす」だ。造り手の想いも、その味わいもしっかりと記憶に刻み付けるようにして飲んでいる。記憶がすっ飛ぶ癖はいまだ健在だが、その味は翌日になっても絶対に忘れていない。クラフトビールはわたしにとってそんな存在なのだ。
※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。