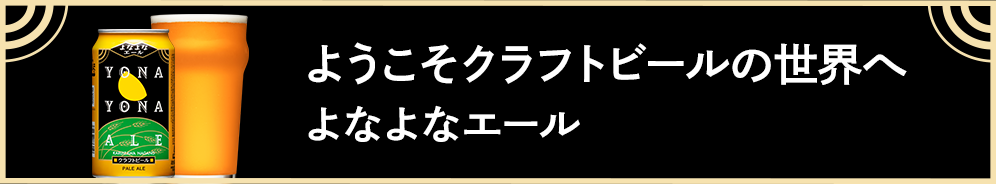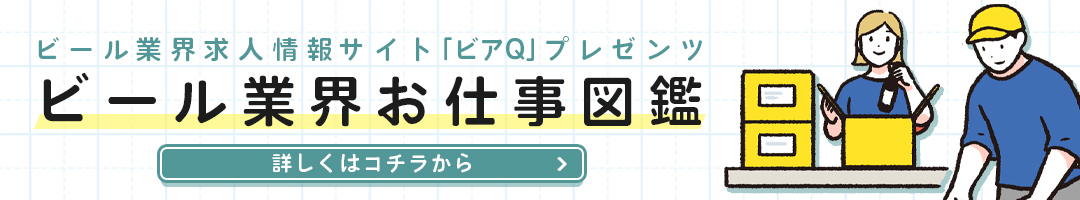【連載ビール小説】タイムスリップビール~黒船来航、ビールで対抗~③
ビールという飲み物を通じ、歴史が、そして人の心が動く。これはお酒に魅せられ、お酒の力を信じた人たちのお話。
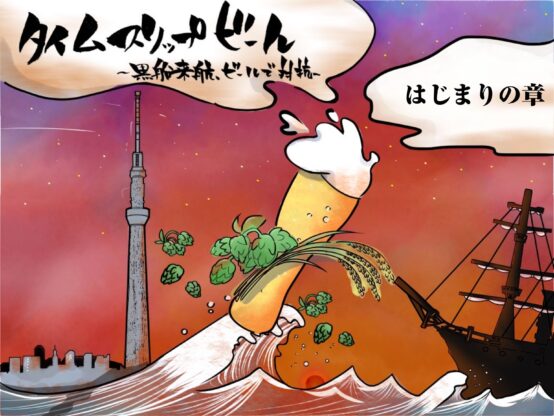
前回のおはなしはこちら
「まああれだけ飲めば、さすがに潰れるってもんよね」
夜もとっぷりとふけた頃。客足の引いた店の床では、なおが昼間と同じように寝転んでいびきをかいていた。ごうごうと鳴り響く音は、まるで地鳴りのようだ。
「それで?どうするつもりなの?この人」
つるは眉をひそめ、喜兵寿に向き合う。もともと鋭い目つきのつるだ。それがギッと睨みつけてくるもんだから、その眼光は痛いほどに鋭かった。
「そうだなあ……まあとりあえず明日の朝にはどうにかするよ」
「まったく。お兄ちゃんはそんな見た目してるくせに人が良すぎるよね」
つるはやれやれといったように、大きくため息をつく。
「見た目はヤクザ、中身は母ちゃん。常連さんたちが言ってるけど、本当その通り。まあそこがいいとこなんだろうけどさぁ。そろそろ閉店時間でしょう?わたしおもての暖簾おろしてくる」
つるは大きく伸びをしながら、外へと出ていった。
「すまんな」
喜兵寿はつるの背中を見送ると、戸棚の下から先ほどの瓶を取り出した。つるりとした表面に手を這わせ、瓶の口に鼻を近づけると深く息を吸う。
「何度嗅いでも不思議な酒だ。ああ、あの時もっとしっかり味わっていれば……!」
喜兵寿は自他共に認める「酒狂い」だった。酒狂いといっても別に大酒を飲むわけではない。とにかく酒というものが熱烈に好きで、近隣の酒は新酒も含めすべて飲み漁り、気になる噂を聞けば何日かけてでも飲みに行っていた。
酒はその酒蔵の個性が色濃くでるものだ。蔵人の技、各蔵付き酵母の表情、。そういったものが溶け合ってできる酒は、飲めばそこに刻まれているすべてがすぐにわかる。「この酒蔵はあそこの弟子が独立して創った酒蔵か」とか「この新酒を仕込んだのはあそこの酒蔵か」だとか。しかしなおの持っていた酒は、すべてが未知で味わったことがないものだった。口にしたことのない酵母の香りに、米では決して表現できないような香ばしさ。そしてあの舌の痺れるような不可思議な感覚……そのすべてを喜兵寿はどうにかしてもう一度味わいたくて仕方なかった。
(得体のしれない男だが、こいつと一緒にいればまたあの酒が飲めるかもしれないな)
一滴でも酒が残っていないかと瓶の中を覗き込んでいると、外からつるの大きな声がした。
「ちょっと、一体なんの用ですか!」
喜兵寿が急いで表に出ると、数人の男たちが店の前に立ちふさがっていた。
「おう、柳やの旦那。ひさしいな」
がっしりとした身体に、狡猾そうに光る目。そこにいたのは下の町の岡っ引きである村岡だった。後ろに控える手下は3人。どいつもこいつもやたらとガタイがよく、気持ちの悪い笑みを口元に浮かべている。
「今日はもう店じまいだよ。酒は売り切れだ、さっさと帰ってくんな」
喜兵寿が下から睨みつけるようにいうと、村岡は「おお、こわ!」と両手を挙げた。
「別に今日は旦那に用があって来たわけじゃない。実はこの町におかしな輩が迷い込んできたと通報があってね」
村岡は笑みを浮かべたまま、喜兵寿の肩に手をかけた。厚みのある手のひらが、ぐぐっと肩にのめり込む。なんて力だ。喜兵寿は肩の痛みに思わず顔をしかめる。
「おかしな格好をした輩がうろついていたんじゃあ、下の町の皆さんも安心できないだろう?町の安全を守るのが我々岡っ引きの仕事だ。これは大変と、こんな夜更けにわざわざ出向いてきたってわけだ」
村岡は喜兵寿の肩を思いっきり突き飛ばすと、どすどすと店の中に入っていった。手下たちもにやにやしながらその後に続く。
「なに人の店に勝手に入ってんだ」
ぼそっと呟き、その背中に殴りかかろうとした喜兵寿を、つるが必死に止めた。
「やめなって、お兄ちゃん!こいつらに手をだしたら、罪をでっちあげられて牢屋敷にいれられちまう。牢屋敷になんて入っちまったら店がつぶれちまうよ」
数か月前にやってきた岡っ引き、村岡の悪評は下の町でも有名だった。「町の治安が」などと耳障りのいい言葉を並べ、気に入らない人間をどんどんと牢屋敷送りにしていると聞く。村岡の雇い主である人物が権限を持つが故、誰もが疑問を持ちつつも口出しをすることができないのであった。
「……くそ」
喜兵寿がギリギリと歯を食いしばりながら店の中に入ると、床で眠るなおを岡っ引きたちが取り囲んでいた。その手には刀が握られており、行燈の光に照らされ、なまめかしい殺気を放っている。
「ほう、これはまた噂通りの珍妙な輩だな。やはり異国のものが迷い込んだか」
村岡はなおをまじまじと見つめていった。
「おい、起きろ!お主はなにものだ」
村岡が大きな声で叫ぶと、なおはパチリと目を開けた。
「ふぁあ。やべ、また眠っちまったかあ。飲みすぎた」
大きなあくびをしながら身体を起こす。なおが動いたことで、男たちの構えた刀の切っ先に力が入るのがわかった。人の殺意とはしばしば目に見えるものだ。「何かしでかしたら斬る」という意思が空中に漂うのを感じ、喜兵寿はごくりと唾を飲んだ。この男のことはよく知らないが、この男が死ねば、もう二度とあの酒を飲むことは叶わなくなってしまう。
(おかしなことをしないでくれよ……)
そうなおに祈りつつも、心のどこかではこの男がおかしなことをしないわけがないだろうなあ、という諦めに似た気持ちもあった。
「お主名はなんと申す」
「こっちは酔っぱらってんだっつーの。寝起きにでかい声出すとかどうかしてんだろ、おっさん。ってか水くれよ。みずーみずー」
ガシガシと頭をかくなおに、喜兵寿は「やっぱりな」と心の中で大きなため息をついた。
「おい!村岡さまに無礼がすぎるぞ!」
手下たちの大声で、なおはやっと自分が刀を向けられていることに気づいたようだった。
「なに物騒なもん人に向けてんだよ。どうせ偽もんだろけどよ」
そういって軽く切っ先に触れると、その指からは血がたらりと垂れた。
「げ、うっわまじか!え?ちょっと待てって。なんだこれ」
「もう一度聞く。お主、名はなんと申す?」
「え、あっと、久我山……久我山 直也です」
酔いが一気にさめ、状況が飲み込めてきたのであろう。「やばい、本物じゃん」などと呟きながら、目を白黒させている。
「直也、その姿によく似合うおかしな名だな。時に直也、お主は何者じゃ?どこから来た。返答次第ではここで叩き切る」
「ちょっ、え、えっと、月島ブルーイングのブルワーで、ビールを造ってます」
村岡は眉間に皺を寄せると、「わけのわからんことをいうな!」と大きな声を出した。
「聞いたこともない言葉を使うとは、お主の異国のものに違いないな!!!」
「いや、ちがくて!つまり、えっと……自分は日本人で、ビールはお酒の一種で。ビールはこの国のお酒じゃないんですけど、それをつくってる自分は日本人です」
しどろもどろのなおの説明に、一瞬村岡の顔色が変わった。
「……お主、いま異国の酒を造るといったか?」
その姿を見て、喜兵寿は数日前の店での会話をハッと思い出した。蘭学者である幸民先生がべろべろになって周りの男たちに話していたのだ。
『あの黒い船は異国の力そのものを示しているわけでな。たんまり見たこともないものが乗っているわけよ。聴いたこともない音色を奏でる楽器に、食べたこともない美味なるものに、飲んだこともない美酒もあるらしいぞ。そんなもんに囲まれて海を渡ってきたやつらにどうやって太刀打ちするかを、お上たちは考えているらしい。生半可なもんじゃかないっこないだろうからなあ!わしもここで一旗あげてやろうと情報を集めているわけだ。まあ、まずは酒だろうな。うまい酒さえあれば、大抵のことはうまくいく』
もしもその話が本当で、異国の酒が造れるものをお上が探しているのだとすれば……喜兵寿は大きく息を吸い込んだ。
「そうだ、なおは異国の酒を造る杜氏だ。わたしの遠縁のものでな、南方からはるばる呼び寄せた」
「ほう?」突然話し出した喜兵寿を、村岡が睨みつける。
「なおが造る『びいる』なる酒は、江戸では見たこともない代物。その奇妙なる味わいの酒は、異国では重宝されるものと聞く。そんな類稀なる酒を造れるものが、多少おかしな格好をしていても不思議はないだろう。わたしとなおはこれから『びいる』を造る予定だ。どうだ、いまだかつてない美酒を飲んでみたくはないか?」
村岡はしばらく黙って何かを考んでいたが、にやりと意地悪そうに笑うといった。
「いいだろう。ではその『びいる』とやらを造ってみせよ。しかしもしも今の話が虚言だった場合、お主たちは牢屋敷送りとさせてもらう。小伝馬町の牢屋敷は死ぬよりも辛い場所と言われておるからのお。いや、牢屋敷に入れば皆半月も持たずに死んでしまうんだがな」
村岡はにやにや話しながら、手下たちに刀を下ろさせた。
「それで?酒は幾月ほどでできるのか」
「……半年ほどで」
「そんなには待てぬ。三か月でどうにかせよ。では、その『びいる』とやらを楽しみにしておるぞ」
そういうと村岡はドスドスと足音を鳴らしながら店を出ていった。
「ちょっと!お兄ちゃん、何言ってんの?!」
岡っ引きたちがいなくなると、つるが鬼の形相で喜兵寿の着物を掴んできた。恐ろしかったのであろう、手にはびっしょりと汗をかいているのがわかる。
「すまん、しかしあのままではなおが斬られていたかもしれないだろう」
「だからと言って……ねえちょっとあんた!『びいる』本当に造れるんでしょうね?!」
つるに話しかけられても、なおは茫然とした表情のまま床に座っていた。
「俺本物の刀初めてみたわ。やべえ威力だ。こっわ」
「ちょっと!!!」
喜兵寿は荒ぶるつるを座敷に座らせ、床に座り込んだままのなおに手を差し伸べた。
「おいなお。確認なんだが、お主は『びいる』を造れるんだよな?聞いていたと思うが、『びいる』を献上しなければお主も俺も死ぬことになる」
「ああ、それは大丈夫だ。なんたって俺は売れっ子ブルワーだからな。最高にうまいビールを造って、あいつらをびっくりさせてやろうぜ」
そういって喜兵寿の手をとったなおは、小刻みに震えていた。
「喜兵寿助かった、まじでありがとうな」
喜兵寿が安堵の息をつくか、つかないかのうちに「念のための確認だけど」となおがいった。
「この時代って、ホップある…よな?」
「ほっぷ?なんだそれは」
喜兵寿が眉間に皺を寄せる。
「え、じゃあさすがに麦芽はあるよな……?」
「は?そんなもん知らぬ」
「まじか……」
なおの顔からはすうっと血の気が引き、それで状況を察した喜兵寿の顔からも血の気が引いて行った。
「ホップも麦芽もなかったらどうやってビール造るんだよーーーー!」
ビールを造らにゃ殺される。
されどもそれは険路。
こうしてなおと喜兵寿の、ないないづくしのビール造り紀は幕を開けたのである。
―続く
※このお話は毎週水曜日21時に更新します!
※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。