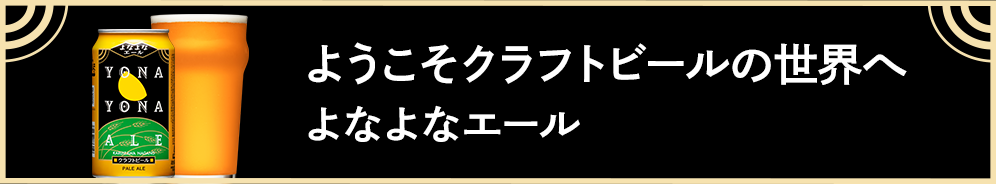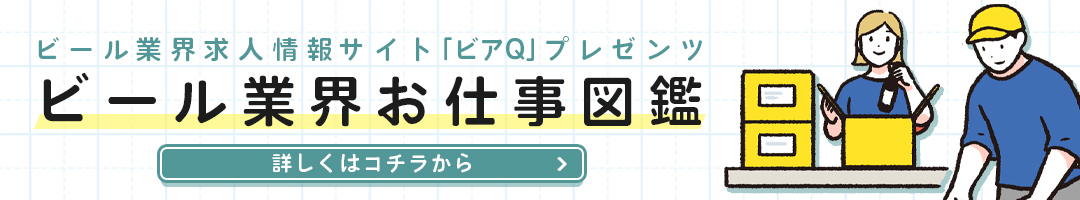ビールを知的エンターテインメントとして楽しく伝え広める【Beerに惹かれたものたち17人目 サッポロビール株式会社 端田晶氏】
「日本ビール検定」。ビールファンならば1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。「一般社団法人 日本ビール文化研究会」が年に1度主催している検定です。そこで理事顧問を務めているのが、サッポロビール株式会社(以下、サッポロビール)文化広報顧問の端田晶氏です。通称「びあけん顧問」として数多くの著書やメディア出演を通じてビールの歴史を伝えていらっしゃいます。端田氏は、なぜビール史に興味をもったのか? なぜ伝え続けているのか? その思いを知るため、彼の元を訪れることにしました。
目次
■テスト的に覚えるのではなく、知的エンターテイメントとして日常で使える雑学に
「ビールを知的エンターテイメントにするためのツールですね」。
端田氏にとってビール史はどんな存在なのかを聞くとこのように答えてくれました。
「美味しさだけではなく、ブランドがどのように育ってきたのかがわかると味わいも変わってきます。舌で美味しいとか目で映えるだけではなく、頭脳を使って楽しむためにビール史は大事なものと考えています」と、ビールを美味しく飲むためにストーリーを知ることは重要な要素といいます。
知的エンターテイメントとして伝えるときに何を意識しているのか尋ねると「飽きさせないこと。誤解を恐れずにいうなら年号はさほど重要ではなくて、重要人物のドラマにスポットを当てて伝えると興味をもってもらえます。営業職の人に話をするなら営業先でちょっとした雑談に使えるドラマを教えてあげる。楽しんで覚えられた方が良いですからね」と、こだわりを教えてくれました。

ビール史への思いを話す端田氏。
■味よりもブランドの歴史に関心が強い時代。結果的に歴史を知る必要があった
端田氏がサッポロビールに入社したのは1980年。営業や広報、経営戦略の仕事を経て2004年9月に経営戦略本部コーポレートコミュニケーション(現 広報部)部長に就任。何がきっかけでビール史に関心をもつようになったのだろうか。
「当時、部長は『恵比寿麦酒記念館』の館長を兼任することになっていましたが、広報の仕事が忙しく記念館の業務に時間を割くことが難しい状況でした。でも周囲の人は広報部長よりも記念館の館長の方に関心があって、飲食店にいくとスタッフさんがお客さんに『この人は恵比寿麦酒記念館の館長です』って話をするんです。そうするとお酒が入って気分を良くした人がいろいろ質問してくる(笑)。そのなかで歴史の話をよく聞かれました。雑学の話をするにしても『どうしてそうなった』と、歴史について説明をしないと伝わらない。歴史ドラマは好きでしたが、自ら年号を覚えるのは苦手でした。最初は面白くなかったですよ。でも、立場的に答えないわけにはいけませんから勉強をはじめました。流れが理解できるようになってきて面白さが感じられるようになってきました」。

覚えることに苦手意識があったとは意外だった。
意外にも歴史は苦手だったという。しかし、マーケティングで培った経験もあったのでしょう。人々が何を求めているのかを的確に捉えて提供していくことで期待に応えていきます。
その後、2006年にCSR(Corporate Social Responsibility ※1)部長、2011年に社長付を務めたときに特命で社員に歴史を話す仕事を請け負います。
「弊社の130年(社長付になった当時)以上の歴史をきちんと把握していない社員もいて、経営陣は明治時代の志を伝える求心力として私に期待していました。現在まで続く協働契約栽培の話をするとき、大元に北海道の開拓使があり、農業を大事にして原料にこだわってきた会社だということを語ってほしいと要望がありました。海外企業の買収が話題になっていた時期で、そこを含めて考えていこうと企業史をテーマにしました。『日本ビール検定』を受検するわけではないので、研修では『流れを理解しないさい』と伝えて、時間も120分のうち30分をグループワークと発表にして考える内容にしました」。
社内研修を続けていくと外部からも声がかかり、社外でも話をすることに。そこでは歴史以外に美味しくビールを飲む方法も伝えるようになります。
※1 自社利益のみを追求するだけではなく、経済、環境、社会など幅広い分野での社会全体のニーズの移り変わりを捉え、迅速に価値創造や市場創造に結び付け、経済の活性化やより良い社会づくりを目指す自発的な取り組み。
■海外出張中に起こった世界的大事件。それが長いビール人生で最も衝撃を受けた
今年で入社して40年を迎える。昭和、平成、令和と長い月日をビールとともに歩んできた端田氏。1番印象に残っている出来事を聞いてみました。
「天安門事件ですね。当時は海外ビールの輸入に携わっていて、『青島ビール』も担当でした。その日はロンドンに出張をしていて、ホテルの部屋にきた朝刊の見出しを読んで驚きました。それで『現地はどうなっているんだろう?』と料金が高くて会社から使用が認められていなかった国際電話で上海や北京の日本大使館や青島ビールに連絡を入れたのですがつながらない。そのころの『青島ビール』は国営企業で国の情勢が変わると取引に影響が出てくる。様々な状況になることが頭の中に駆け巡って連絡が取れるまでの時間は混乱しました。まぁ、結果としては何もなかったんですけど、未だに夢でみるくらいインパクトのある出来事でした」。
「スーパードライ」の出現や小規模醸造の解禁と日本のビールシーンに変化をもたらしたことが聞けるかと思いましたが、天安門事件が出てくることは予想外。余談ですが、「スーパードライ」については「海外ビールを担当していたので、あまり関心がなかった」とのこと。

天安門事件のことを振り返る端田氏。
■単純なマーケティング思考では人の心をつかめなくなってきた。これから面白くなっていく
現在、そしてこれからのビール界についても聞いてみました。
「ビールは嗜好品ですから本来はマーケティングだけで進めてしまうのは幸せなことではありません。大手はマーケティングを強く志向するがゆえにものが言えなくなってきました。メイン商品であろうともブラッシュアップをしてリニューアルをしますが、具体的に変わった点を言いにくい環境になっています。その結果として『美味しくなりました』とか抽象的な表現でしか伝えられなくなっています。その一方で、小規模ブルワリーの醸造家たちが具体的な表現で「モノ」「味」を語り、また具現化したりして、これに呼応して新しいファンが形成されつつあり本当に面白くなってきたと思います」。
飲み手が思いを主張するようになってきたことについて、「これはとても楽しい反応で、この先もっと楽しくなると予想しています」と、自らの思いを声にする人たちが生み出すエネルギーが大手ビールメーカーの考え方にも変化を起こす可能性があるといいます。
「日本ビール検定」でも20代女性の受検者数が増え、若い世代が「映える」だけでなく知的エンターテイメントとしてビールを楽しめるようになってきた状況を「嬉しい」と話します。

市場が縮小しており、閉塞感のあるビール業界だが、端田氏からみるとこれからが面白いという。
■自分ができる分野を明るく照らし、ビールに興味をもつ人を増やしたい
「今後やりたいことは、馬越恭平を小説にすることと「一隅を照らす(※2)」ことですね。私でしたらビール史や『日本ビール検定』を含めて、ビールをもっとわかりやすく楽しく伝えていきたい」。
自分にできる範囲を照らすことで、ビールに関心をもつ人を増やし、その人たちがさらに様々な分野を照らしていけば面白いことがたくさん出てくるといい、1つに深く浸っていくと社会全体も見えてくると語ります。
※2 最澄の言葉。お金ではなく、多くの人が気づかないような片隅で社会を照らしているような人が国の宝という考え。注目されなくても自分の置かれた環境で最善を尽くすことが大切という意味。
「知的エンターテイメント」というように話のなかに「すぐに使える雑学」が組み込まれているので、楽しく学べるのが端田流。今回の取材でもたくさんの話を聞くことができました。これからも一隅を照らし続けて私たちのビールライフを豊かにしてくれることでしょう。
端田氏の話は「日本ビール文化研究会」主催のイベントや講演で聞くことができます。興味のある方はチェックしてください。

◆端田晶(はしだ あきら)氏プロフィール
・サッポロビール株式会社文化広報顧問
・一般社団法人「日本ビール文化研究会」理事顧問
1955年、東京生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒。飲食店アルバイトから酒好きが高じてサッポロビールに入社。ギネス、ミラー、青島など海外ブランドビールのマーケティング、黒ラベルなどの宣伝制作、グループ全体の広報・IRなどを担当。広報IR室長、コーポレートコミュニケーション部長、恵比寿麦酒記念館館長、CSR部長などを歴任。現在は、サッポロビール株式会社文化広報顧問。また、一般社団法人日本ビール文化研究会理事顧問として、同法人主宰の「日本ビール検定」などを通してビール文化の啓蒙に取り組んでいる。通称『びあけん顧問』。随筆集『小心者の大ジョッキ』(講談社:2006年)をはじめビールや酒に関する著書多数。NHK Eテレ「知恵泉」「美の壺」、BSジャパン「武田鉄矢の“昭和は輝いていた”」などTV出演のほか、新聞社の政経懇話会などでの講演も多い。面白く楽しくビールを語る試みとしてライブハウス等での「トークショー」を開始し、好評を博している。2016年には三遊亭兼好師の独演会にゲスト出演し、演芸史上初の「ビール漫談」を披露した。2018年には著書『ぷはっとうまい日本のビール面白ヒストリー』を原作とした映画『日本の麦酒歴史(ビールヒストリー)』(制作:重富寛)が公開された。
※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。