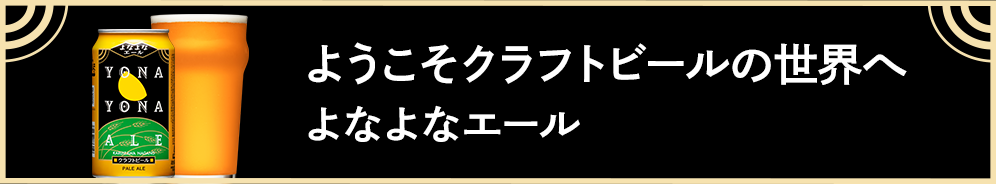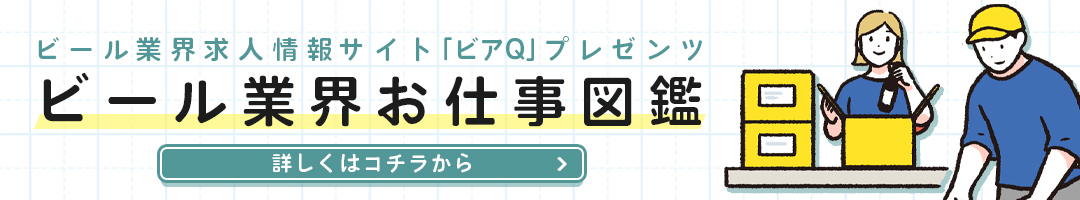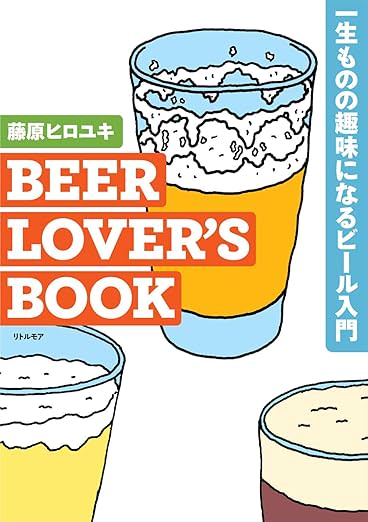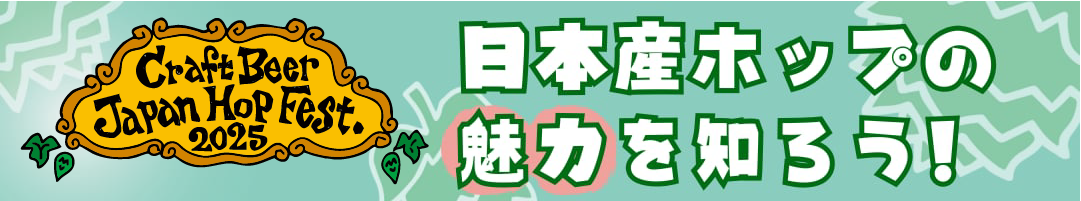【連載ビール小説】タイムスリップビール~黒船来航、ビールで対抗~ 幕間|空即是色 前編
ビールという飲み物を通じ、歴史が、そして人の心が動く。これはお酒に魅せられ、お酒の力を信じた人たちのお話「タイムスリップビール~黒船来航、ビールで対抗~」のサイドストーリー。

本編はこちらから
「かわいいね」
いままで何百回と言われた言葉。おぞましく、ねっとりと貼りつくようなこの言葉を振り払うよう、夏は山の中を走り続けていた。
家を飛び出してきた。いや、正確には本当の家ではなく「引き取られた家」だ。腐った泥のような、思い出すだけでも吐き気のする場所。
昨年両親が死に、夏は地主の家に引き取られた。
「なんとかわいい子だろうか。さあこっちへおいで」
そういって地主は度々夏を部屋に招き入れた。でっぷりと太った腹に夏を乗せ、ごつごつとした手で髪を撫でる。
6歳だった夏は、ただ愛でられるままにこにこと笑っていた。「かわいい」は両親から愛情とともにたっぷりと与えられた言葉だったし、純粋に嬉しかった。しかしその「かわいい」と地主の言う「かわいい」が全く別物だった。
ぼんやりとした違和感が輪郭を持ち始めた頃、夏は鏡に映った自分の姿を見ると頭が痛くなるようになっていた。
華奢な手足に、真っ白な肌。柔らかく潤んだ大きな目に、筋の通った小さな鼻。
そのどれもが歪んで、どす黒くて、忌々しかった。だから逃げたのだ。こんな場所にいるくらいなら、どこかで野垂れ死んだ方がましだった。もう二度と地主の部屋に足を踏み入れたくはなかった。「かわいい」という言葉を耳元で聞きたくなかった。
どのくらい走ったのだろう。履いてきた草鞋は切れてしまった。ゼイゼイと耳の中から聞こえる自分の呼吸と、血のにじむ足の裏。気づけば日はだいぶ傾き、あたりは紅色に包まれ始めている。
夏は木の根に足をとられ、盛大に転んだ。打ち付けた頭がジンジンと痛む。
(ああ、もう無理だな)
一度横になったことで、自分がどれだけ疲れていたか認識してしまった。ひたすら走ってはきたが、ここから行く当てがあるわけではない。夏は夕暮れの中に浮かぶ白い月をぼんやりと眺めた後、瞼を閉じた。
「ちょっとあんた、こんなところでなにしてんの?!」
どのくらいの時間が経ったのだろうか。突然頭上から声が聞こえ、夏は驚いて目をあけた。薄青の空気の中、籠を背負った女の子がこちらを覗き込んでいる。
「大丈夫?立てる?」
猫のような顔の子だな。それが第一印象だった。大きく吊り上がった目、そして喋る度、口元から八重歯が覗く。夏はコクンと頷くと、女の子が差し出した手を取った。
「最近ここいらは質の悪いイノシシが出るんだ。こんなとこで寝てると死ぬよ!あんた家は?」
夏が黙って首を振ると、女の子は「あ、そう」と頷く。
「訳アリってわけね。じゃあ一緒に行こうか」
夏が驚いた顔をすると、女の子はおかしそうに笑った。
「あんたの目、飛び出そうな程にでかいね。心配しなくていいよ。うちも親いなくてさ。今は寺にお世話になってんの。住職いいやつだから安心してきなよ」
女の子は夏の手を強く握る。
「わたしはねね。あんたは?」
「……夏」
「ふうん。いい名前じゃん。さ、早くかえろう」
歩くこと半刻ほど。山の中の寺には、ねねの他に3人の身寄りのない子供たちがいた。住職はびっくりするほど長くて白いひげを生やしていて、みんなに「仙人」と呼ばれていた。
ねねに連れられ、寺に行った日。住職は何も聞かずに夏を寺に招き入れ、あたたかなきのこ汁を食べさせてくれた。
パチパチと燃える火、そして入口に積み上げられた藁のやわらかなにおい。そこには不思議な安心感があって、気づけば夏はねねにもたれかかるようにして眠っていた。
薄れゆく意識の中で、住職の声がぼそりと聞こえたのを覚えている。
「好きなだけここにいればいい」
―続く
※このお話は毎週水曜日21時に更新します!
※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。