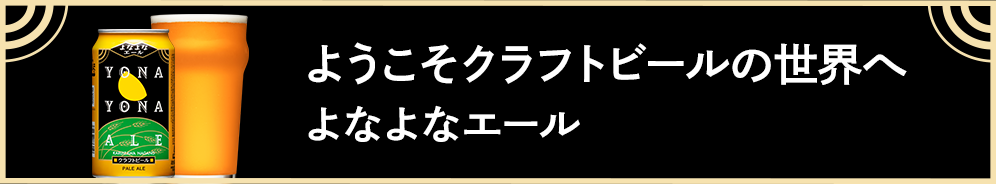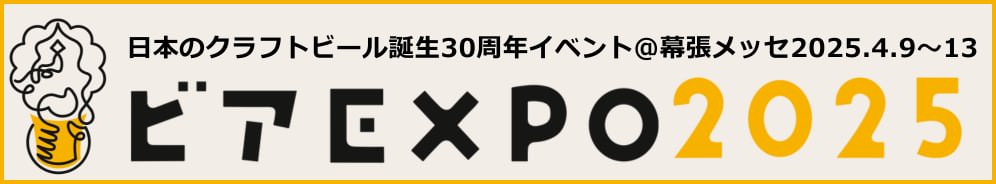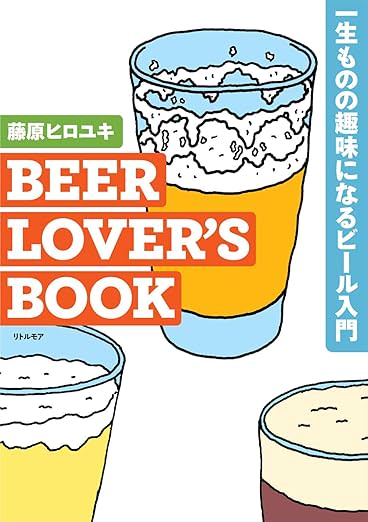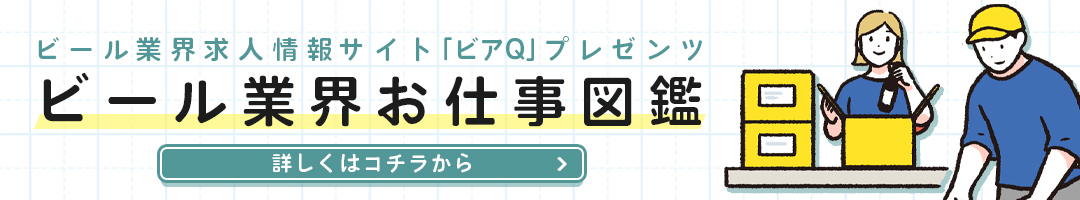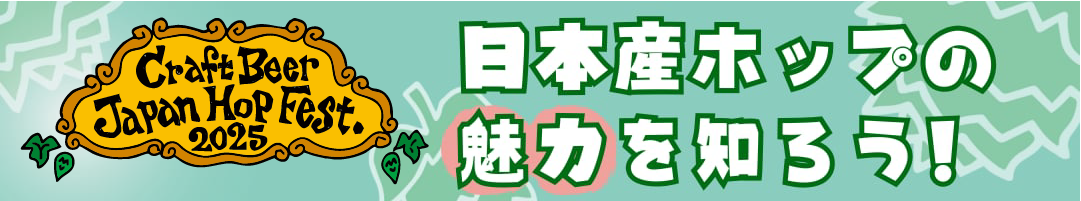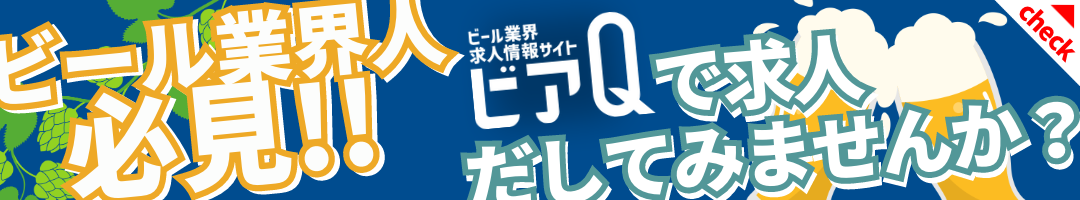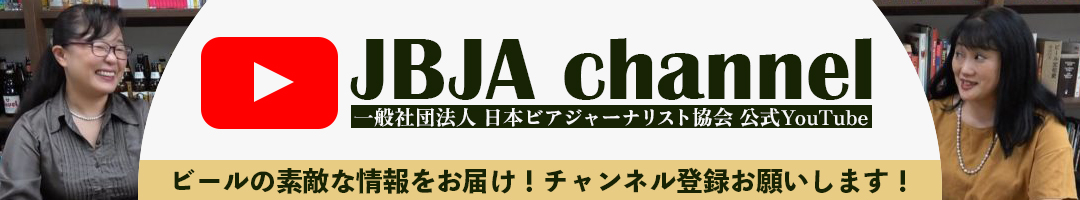スキーとビールと新幹線。最高の1日。

早朝の東京駅、新幹線の改札口は早くも各地に向かう人たちで賑わっている。上越新幹線のガーラ湯沢行きの列車が停まっている20番線のホームに上がると、スキーやスノボを持った人たちが続々と列車に乗りこんでいる。私もその中の一人だ。スキーとブーツを担いだままホームの売店でおにぎりとお茶を買いこんで、車内へと入る。ほぼ満席の車内は、すでにお弁当を広げている人や仮眠モードに入っている人など、様々である。私も荷物置き場にスキーを置いてから、席について、おにぎりを頬張っていると、程なく列車は静かに動き出した。

おにぎりを食べ終えて一息ついているうちに、列車はガーラ湯沢駅に到着。東京駅からわずか1時間11分。速い、速すぎる。乗り鉄の私は、もう少し新幹線に乗っていたい気持ちもあるが、同時にスキーに気がはやる気持ちもある。頭を乗り鉄モードからスキーモードへと切り替えることにしよう。雪の多い今年の冬、駅の周りにも高く積もっている。張り詰めた寒さが心地よい。空は晴れて風も弱く、絶好のスキー日和である。

ガーラ湯沢スキー場はオープンしてから30年以上経つが、来るたびにその便利さに感動する。なにしろ、新幹線の駅がそのままスキーセンターなのである。しかも、東京駅から1時間余り。改札口を出たら目の前にリフト券売り場、少し歩けば更衣室とロッカー。さらに飲食店、土産物店、スキー用品店、スイーツの売店、さらにスパまである。アクセスの良さと充実した設備で、現在はインバウンド客に人気のスキー場となっている。ただ、今はまだ朝の8時過ぎ。インバウンド客で賑わうのは、東京のホテルをチェックアウトしてから来るであろう10時頃からで、今の時間を占めているのはガチのスキーヤーやスノーボーダーである。

更衣室で着替えて、ロッカーに荷物を押し込んで、まず乗るのはゴンドラだ。スキーセンターの場所は標高約360メートル、そこから一気に標高約800メートルのレストハウスまで上がる。そこが、このスキー場の実質的なベースとなる。

ゴンドラを降りると目の前にゲレンデとリフト乗り場。ゲレンデを前にすると、気分もアガってくる。このスキー場は湯沢エリアの中では標高の高い場所にあり、雪質も良い。早朝の綺麗なバーンを狙う人たちで、すでにリフト乗り場には行列が出来ている。自分も、ブーツのバックルを締めなおして、いざリフトへ!

このスキー場は中央・北・南の3つのエリアに分かれているが、今いるのは中央エリア。最初に乗ったクワッドリフトから見下ろすのは、メインコースの「エンターテイメント」である。初級・中級向けのこのコースは最も人気のコースで、一日中多くのスキーヤーやスノーボーダーで賑わっている。

私のお気に入りは南エリアだ。中央エリアから連絡コースを通って南エリアに入ると、格段に人が少なくなる。南エリアには初級者用のコースが無いので、中級以上のスキーヤーやスノーボーダーしか来ないからである。特にお気に入りのコースは「イライザ」。程よく幅のある中斜面が大きなS字状に伸びており、空いているので周りに気を使うことなく自由に滑ることができる。カービングで大きめのターンが好きな私にはちょうど良い。

南エリアには非圧雪の上級者用コースもいくつかある。この「ブロンコ」はリフトからよく見えるので、腕に(脚に?)覚えのある上級者が、これ見よがしにザクザクと滑っていくのを見るのが楽しい。時々、難儀している人を見かけることもあるが。このようなコースは、私も若いころは果敢にチャレンジしたものだが、残念ながら楽しいと思える程の技術は無かった。最近は歳もとり筋力も落ちてきたし、ケガも怖い。君子危うきに近寄らず。君子とは程遠い私だが、今は高みの見物をきめこむだけである。

南エリアで5~6本滑って満足したので、気分を変えようと中央エリアに戻り、このスキー場のトップへ行ってみる。高津倉山の山頂付近からのコース「グルノーブル」は、晴れた日の眺めが最高だ。魚沼盆地と越後山脈をはるか遠くまで見渡すことができる。尾根のコースなので左右の視界も広く、開放感あふれる雰囲気を楽しみながら滑ることができる。

他のコースにも行ったり来たり、休憩も挟みながら滑り続けて、気づけばもう午後2時頃。脚も疲れがたまりつつあるので、そろそろ上がりモードに入る。いや、もしかしたら、これからが今日のメインイベントと言えるかもしれない。待望の美味しいビールが、私を待っている。レストハウス「チアーズ」には複数の飲食店があり、1階はカレーやラーメン、丼ものなどがメインのスキー場らしいフードコートだが、2階にあるレストランが秀逸である。その名も「新潟ご当地レストラン 新潟食道」。タレカツ、わっぱ飯、へぎそば、新潟三大ラーメン、などなど、新潟の美味い物が勢揃い。さながら、デパートの催し物「新潟うまいもの祭り」のイートインコーナーのようだ。

そして、うれしいことに、ビールもサッポロビールの新潟限定商品「風味爽快ニシテ」を飲むことができる。ビールの歴史を勉強したことがある人ならば、中川清兵衛の名を聞いたことがあるだろう。1876年に札幌で開拓史麦酒醸造所が設立された時の、醸造技師である。この人物の出身地は現在の新潟県長岡市。1877年に冷製「札幌ビール」が発売された時のキャッチコピーが「風味爽快ニシテ、健胃ノ効アリ」。時は下り、開拓史が廃止された後に、ビール醸造所は1886年に大倉喜八郎が受け継ぎ、現在のサッポロビールの礎ができたのであるが、この人物も新潟県新発田市の出身である。
かように、サッポロビールと言えば北海道のイメージだが、実は新潟県との縁も深いのである。新潟の酒と言えば日本酒、淡麗辛口の味わいで有名だが、このビールもキレのあるスッキリとした喉越し。新潟の日本酒の味に通じる気がする。その味の特徴は言うまでもなく、新潟の食との相性が抜群なのである。

アテに選んだのは「栃尾揚げ」。新潟県長岡市の栃尾地域の名物である。極厚の油揚げと言うべきか、やや薄めの厚揚げと言うべきか。生姜・刻みネギ・かつお節と、3種の薬味がたっぷりと載っているのがうれしい。タレは小皿で出されているが、一気に全体にかけてしまう。一口ごとに薬味の比率を変えながら食べすすめると、最後まで飽きることがない。ペアリングの形式としては、脂っこい料理をビールで洗い流す爽快さである。スキーで疲れた体に栄養補給も兼ねて、生き返るような心持ちだ。

飲んでしまっては、さすがに本気のスキーは危ない。仕上げに初級者コースを数本滑って、上がることにした。スキーセンターに戻り、着替えて荷物をまとめた後は、帰りの新幹線での一人宴会のための買出しである。

土産物店の入口のすぐ横には、「風味爽快ニシテ」の3缶セットが手提げ袋に入っており、その隣にはエチゴビール専用のショーケースがある。大手の缶ビールやハイボールなども奥のショーケースで売られているが、このように新潟のビールが土産物店の目立つ場所に置かれているのは、ビールファンとしてはうれしい限りである。

今日の1本はこちら。妻有ビールが製造したガーラ湯沢のオリジナルビール「みんなのエール」である。新潟県十日町市のブルワリーである妻有ビールが地元で育てたホップに、ガーラ湯沢で育てたホップも加えて造った、フレッシュホップエールとのことだ。スキーの帰りの新幹線で飲むビールとしては、最高の環境ペアリングである。ビールに駅弁も買い込んで、帰りの車内の人となる。

選んだ駅弁「湯沢わらじたれカツ弁当」は、加熱式の弁当である。ごはんとカツが入った皿の下に石灰と水の袋が入っていて、ヒモを引っ張ると袋が破れて石灰と水の化学反応で発熱し、10分程待つと、アツアツの弁当が食べられる仕組みである。このタイプの弁当は各地で見かけるが、新幹線の車内でアツアツホカホカの弁当が食べられるのはありがたい。

プラカップを持ってくるのを忘れたのは痛恨の極みであるが、幸い土産物店では紙コップを売っていた。これでもビンから直接飲むのとは雲泥の差である。弁当が温まるのを待つ間、ビールをチビチビ飲み始める。フルーティーなホップの香りが素晴らしく、ついつい弁当を食べ始める前にビールが進んでしまう。時計でキッチリ10分を計って、カツとごはんに箸を入れると、湯気が立ち昇る。タレの滲みたカツは見た目ほど味が濃くなく、ビールと旨味が引き立てあう。ごはんは南魚沼産のコシヒカリ。タレのかかったご飯だけでも十分にうまい。東京駅まであと数十分、ゲレンデの余韻に浸りつつ、ビールと駅弁で至福のひと時を楽しむ。スキーシーズンもそろそよ終盤、あと1回くらいは滑りに来たいな、などと考えながら。
(2025年3月20日・30日取材 写真は全て筆者撮影)
※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。